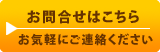2024年4月13日(土)18:00~ @枝光本町商店街アイアンシアター

●『Plant』 劇団言魂
作・演出:山口大器
出演:池高瑞穂、片山桃子、森唯美、横佐古力彰、山口大器
照明:菅本千尋(演劇空間ロッカクナット)
音響:吉田めぐみ
演出助手:瓦田樹雪
稽古補佐:木下海聖(有門正太郎プレゼンツ)
制作:劇団言魂
宣伝美術:山口大器
物言わずただそこに生きている植物と、他を支配し君臨したい人間。この対比と、両者の思いもかけぬ結びつきが面白い。劇団言魂『Plant』は、突拍子もない発想で魅了しながらいろんなことを考えさせる、興味深い作品である。
近未来なのか、パラレルワールドなのか、今の日本とはほんの少しだけ違うどこかが舞台。人々の右手にはマイクロチップが埋め込まれており、それは個人情報管理はもとより他者との関係を築く上で重要な役目をはたしている、そんな時代である。
円(森唯美)が1か月ぶりに実家から恋人・直と同居している部屋に戻って来ると、部屋はもぬけの殻で代わりに大きな植物が残されていた。劇団主宰で探偵業のバイトもやっている友人・優人(山口大器)やその後輩で植物を研究している君丸(横佐古力彰)の協力も仰ぐが、直は見つからない。そんな折に、直のことを知っているらしい女の子(片山桃子)に会い、直がどうやら植物になったのではないかと気がつく…。
面白かったのは、マイクロチップによって「合意」をとるというエピソードである。――自宅に他人(友人であっても)が来る場合に、互いの右手のひらを合わせることで(=マイクロチップをかざすことで)、「招きました/強引に押し入っていません」との「合意」をとる。芝居の稽古において演出家がダメ出しをする際には「問題発言をしていません/傷ついていません」との「合意」をとる――。現実でも2023年末に「性的合意アプリ」なるものが開発されたというニュースを見たのだが、まさに現在と地続きにありえそうなこのフィクションが実に示唆的で面白い。ハラスメントはあってはならないことだが、その一方で加害者になるのを恐れるあまり「問題がないと思っているかどうか」をいちいち確認させてほしいという心理…バランスの取り方が難しい現代をよく表している。すべてにおいて「合意」をとれば解決ではないか!と、短絡的にチップの「合意」に頼りたくなる気分はわかる。いや、この「合意」すら強制的に合意させられましたと言われることもあろう、そのためにチップ所持者の血流や心拍数から心理状態を検知して…? 本作ではそこまでの話はなかったが(心理状態の検知は別のエピソードだった)皮肉な現実味がある。
物語の肝となるのは「人間の植物化」。植物になってしまった直はモラハラ気質だった(そのために円がプロポーズを受け入れられず実家に帰っていた)ことが分かるのだが、優人もまた劇団で過去に強権的だったことが明らかになる。今ではすっかり反省したかに見える優人だが、少しずつ木になりかけている。後輩・君丸への態度からも優人のパワハラ気質は治っているわけではなく…どうやら、支配的で、高圧的な態度をとる人間が植物になっていくらしいとわかる。そのことに納得してしまうのは、ハラスメント加害者に対して「お前は(植物のように)黙れ!」と言いたくなるからだろうか。因果関係なんて一つも説明されていないのに妙な説得力がある。
ユニークなのは優人の植物化していく様子。芽が出て、葉が生え、枝が出て、木になり、足から根が出て張るようになり…変化していくビジュアルはインパクト大。優人役の山口大器の焦る様子が面白さに輪をかけている。物言わず中央に鎮座している大きな木(=直)との対比もあり、最終的にこうなるのだろうと悲劇的な結末も思わせるのに、植物化する優人のビジュアルにやはり笑ってしまう。本人にとっては悲劇だが周りにとっては喜劇、の典型かもしれない。―――と笑って見てはいたが、そして優人が最後の最後までセクハラまがいのことを必死に叫び続けることもあって見ている時は気がつかなかったが、これはいじめの構造にも似ている。他者からの奇異な目に晒されるということ、被害者が言葉を失ってしまうこと、そんな目に遭わされた者たちの復讐が「植物化」ということなのか。
本作は徹頭徹尾、被害者と加害者は分断され、分かり合えないと言っているように聞こえる。例えば直も優人も反省し自分の態度を改善しようと試みていたらしいのにそれでも植物化してしまうという結論。人の根本は簡単には変わらないという絶望の表れだろうか。また、いずれは完全な植物になるのに、それでも火をつけて優人を殺してしまおうとする君丸の姿には、虐げられていた者は加害者を絶対に許さないという悲痛な決意が見える。
となると、「被害者/加害者」と厳密に分かれて、決して分かり合えず、人は変わることがないという、かなりきつめの人生観を持った芝居ともいえる。そんななか登場する桜(池高瑞穂)は怪しげな宗教めいたことを主張するしお近づきになりたくないタイプではあるが、「(マイクロチップに振り回されて、)みんな人を見ることをやめている」といった批判は一理あるし、この芝居を中和する役目を担っていると言えるのかもしれない。
シーンに合わせて天井に吊られてテーブルが降りて来たり、植物化していく様子の美術がよくできていたり、演劇ならではの仕掛けも楽しませてくれた。
2024.05.12
カテゴリー:
2024年3月8日(金)17:00~ /2024年3月19日(火)17:00~ @博多座

●ミュージカル トッツィー
脚本:ロバート・ホーン
演出:スコット・エリス
出演:山崎育三郎、愛希れいか、昆夏美、金井勇太、岡田亮輔/おばたのお兄さん、エハラマサヒロ、羽場裕一、キムラ緑子
音楽・歌詞:デヴィッド・ヤズベック
振付:デニス・ジョーンズ
演出補:デイブ・ソロモン
オリジナル装置デザイン:デヴィッド・ロックウェル
オリジナル衣裳デザイン:ウィリアム・アイヴィ・ロング
翻訳:徐 賀世子
訳詞:高橋亜子
音楽監督・指揮:塩田明弘
日本版装置デザイン:中根聡子
照明:日下靖順
音響:山本浩一
衣裳:中原幸子
ヘアメイク:岡田智江
1982年公開の映画『トッツィー』が40年前の映画であるにもかかわらず今見ても古臭く感じられないのは、「男性が女装すること」のコメディではなく、「男性が女装することで浮き彫りにした社会の矛盾」を笑うコメディだからだ。この映画を、なぜ現代、ミュージカル舞台化するのかと考えると――いや逆に、まだこの映画のテーマが十分に通用してしまうこと、過去の遺物になっていないことこそが問題なのだと気づく。本作、「山崎育三郎の女装」が宣伝として独り歩きしていた感があり一抹の不安もあったけれど、映画同様に(アップデートして)「男性が女装することで初めて見えてくるジェンダー問題」を描いた舞台になっていた。
物語の舞台はブロードウェイ。売れない俳優のマイケル(山崎育三郎)は実力はあるものの自信過剰でこだわりも強く、トラブルメーカーとして仕事を干されてしまう。そんな中、元カノのサンディ(昆夏美)がオーディションを受ける話を聞き、マイケルは女装して「ドロシー・マイケルズ」としてオーディションを受け、合格してしまう。個性的で歯に衣着せず建設的な意見を言う姿は、同じ舞台の仲間にも好評、かつプロデューサーにも気にいられ、あれよあれよと主役に抜擢され一躍大スターになる。共演者のジュリー(愛希れいか)と演技論を交わしお互いのことを知るうちに、マイケルはジュリーに恋をし、ある日思わずキスをしてしまう。マイケルを女性だと思い込んでいるジュリーは戸惑うが、一大決心をして「彼女」の愛を受け入れようとする。ところが…。

映画同様に本作も社会における女性の苦悩を描こうとしている。例えば、女性は「謙虚であること」が求められること(なぜ、自分の意見を言えば「ヒステリー」と言われるのだ?)、「勘違い」させないようにふるまいに気をつけなければならないこと(言い寄られる方が悪いのか?)、若い女性が男に依存せず自らの力で成功する難しさ、などである。正直に書けば、これらに関しては映画の方がしっかりと伝わる。「女性として」目の当たりにしたドロシーが強引な手法で変えていく事で、周囲にも変化が現れるさまが描かれているからだ。一方、舞台である本作は、ジュリーに語らせて「まとめて示した」ように見える。
しかし、映画からアップデートされた部分が興味深かった。例えば、元カノ・サンディが欲しがった仕事(役)を(女装しているとはいえ、男の)マイケルが奪った形になってしまったことについて、親友のジェフ(金井勇太)に「女が男の股間からパワーを取り返す時代に、(女装した)男が女のポストを取り上げるのか」とはっきり批判される(映画ではその点はなぁなぁなまま)。もちろん本作が成り立たないので仕方がない設定だが、ジェンダーバイアスを浮き彫りにする前にこの矛盾について断りを入れておこうという姿勢に、なるほどとうなづく。
また女性の若さに価値を置きすぎる日本において、中年女性であるドロシーが若い男優に一目ぼれされるという設定はなかなかに大きな意味を持つ。「恋愛は若い女性のもの、中年女性が恋愛の対象になるはずがない、ましてや若い男性からの求愛なんて」という偏見を打ち破るインパクトは大きい。それだけでない。ドロシーは言う、「おばさんだって願望はあるのよ」と。中年女性は恋愛において主体にもなるのだという主張は、男性・若い女性のみならず中年以上の当人たちにとっても、当たり前だが新しいメッセージになっている。
ドロシーからキスをされたジュリーが、じっくり考えた挙句に、自分はレズビアンではなかったけれどと言いつつドロシーを受け入れようとする点も、映画との大きな差異で価値がある変更だ。映画ではジュリーはドロシーを拒否する(ドロシーが男性であると明らかにして歩み寄る所で終わる)が、本作はジュリーがドロシーを受け入れる、いや、積極的に欲しいと手をのばす。以前なにかの本に、セクシュアリティはプロセスとして捉えるべきだと書かれていたのを思いだした。「ヘテロセクシュアル/ホモセクシュアル」だから「異性/同性」がほしいのではなく、その相手が欲しいのだという気持ちに従えば、セクシュアリティは絶対の属性ではなくプロセスに過ぎないという――これこそが2020年代だからこその描き方かもしれない。そしてこういったジェンダーやセクシュアリティに関する丁寧なアップデートが、日本にいい刺激を与えるだろう。

最後にキャストについて。昆夏美がとんでもなく魅力的で強く印象に残る。早口で音程の差が激しい難曲『未来が見える』を、ヒステリックにテンション高く、そしてかわいく歌いこなしている。マイケルの親友ジェフを演じる金井勇太も、好感度の高い楽しい存在である。ジュリーに言い寄る傲慢な演出家はエハラマサヒロが演じるが、嫌味なく笑わせてくれる。彼を中心にしたアンサンブルのダンスは真似したいほど面白い。
ただ、個人的には、ドロシー役(女装時)は良いが、マイケル役の山崎育三郎にはピンと来なかった。というのも、自信家で傲慢で性格に難ありのマイケルにしては、山崎の声に色気がありすぎる。二役をやったがゆえに際立ってそう感じられたのかもしれない。
2024.05.02
カテゴリー:

- 2026年1月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 『証明』Level 19
- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇
- 『きらめく星座』こまつ座
- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ
- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi
- 『受胎の森』ゴブノタマシイ
- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house
- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス
- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議
- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●
大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。
2005年~朝日新聞に劇評を執筆
2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆
舞台、映画、読書をこよなく愛しております。
演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。
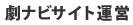
「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。
株式会社シアターネットプロジェクト
https://theaternet.co.jp
〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204