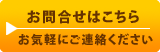2023年6月25日(日)13:00 @北九州芸術劇場・中劇場

●木ノ下歌舞伎
『糸井版 摂州合邦辻』
作:菅専助、若竹笛躬
監修・補綴・上演台本:木ノ下裕一
上演台本・演出・音楽:糸井幸之介
(FUKAIPRODUCE羽衣)
出演:内田慈、土屋神葉、谷山知宏、永島敬三、永井茉梨奈、飛田大輔、石田迪子、山森大輔、伊東沙保、西田夏奈子、武谷公雄
私には心地悪い作品だった。それは、情感たっぷりに謳いあげ、自らの世界に酔いしれている作品に見えたからだ。ちょうど数カ月前に見た同じ木ノ下歌舞伎の『桜姫東文章』(脚本・演出:岡田利規)が、歌舞伎の「常識」を現代の批判的なまなざしを持って描いていたからだろうか、本作が歌舞伎の「理不尽な世界観」をことさらにドラマティックに描いて恍惚としているように見えたのだ。『摂州合邦辻』の世界観は本家(の文楽や歌舞伎)でしっかりと味わえばいい。なぜ同じ世界観をそのまま現代劇でやるのか。その違和感は終始ぬぐえなかった。
『摂州合邦辻』は文楽でも歌舞伎でも人気の演目の一つで、義理の母親が血のつながらぬ息子を愛したことで起こる悲劇の物語だ。大名家の跡取りである俊徳丸は見目麗しく才長けた青年で、継母の玉手御前から異様な愛情を寄せられていた。許嫁もいる彼は継母を拒絶、だが病にかかり何もかも捨てて失踪する。彼は失明し顔も醜く変わり果て町をさまよっていた。許嫁の浅香姫そして気が触れたような玉手御前もそれぞれ俊徳丸を探し求めるが、先に探し出したのは浅香姫だった。2人は僧侶に助けられ匿ってもらう。実はこの僧侶は玉手御前の父親であった。そこに奇しくも玉手御前が実家に立ち寄る。両親に不義の恋をやめるよう諭されるが玉手御前は聞く耳を持たず、逃げ出す俊徳丸たちを見つけ浅香姫に襲い掛かろうとする。仕方なく父は娘の玉手御前に手をかけるのだった。そうして命を無くす寸前に、玉手御前は、全てはお家騒動から俊徳丸と彼の命を狙う腹違いの兄それぞれの命を守るための計画であったこと、俊徳丸の病は自分が飲ませた毒薬のせいで治すには自分の生血が必要だということを告白する。そうして玉手御前は息絶え、俊徳丸は生血のおかげで元通りになるのだった…とまぁ、かなりぶっ飛んだ内容の作品である。
さて本作はラストの父が娘を手にかけるシーンから始まる(時計の秒針音が響いて幕を開けるあたり、ありがちだが分かりやすいとも言える)。それから遡って冒頭から描いていくわけだが、これをミュージカル調に歌をたっぷりと挿入する。この劇中歌が私にはすわりが悪い。俳優たちの歌は聴かせるほどには上手くなく、現代を歌う(字幕もあるのでよくわかる)歌詞のギャップというか唐突感があるからだ。印象的なのが玉手御前とその父(僧侶でもあり、娘を手にかける)合邦道心が二人で見つめ合って「パパ パパ」「娘よ」と歌うシーン。愛されて育った娘、彼女を大切に慈しんできた父親…の関係を示すことが、ラストの「父が娘を手にかけざるを得ない悲劇」をより際立たせるということなのだろうか。逆にそのあざとさが鼻につき、私には残念ながら響いてこなかったのだが…。
舞台美術の糸・球・柱の使い方についても疑問が残る。柱については、縦に横に使い方を変え配置も工夫があり一瞬にして景色を変え優れた使い方だと思ったが、配布資料にあるようにこれらが「世界の様々な神話に出てくるモチーフ」だから使用したというのであれば、ピンと来ない。本作が普遍的テーマを扱っているようには思えないからだ。
それらは全て、「この古典作品を現代劇に作り直す意味」が本公演に見いだせなかったからである。比較するのは本意ではないが、今までに見た木ノ下歌舞伎(木ノ下裕一監修のもと、作品ごとに演出家を変えて、歌舞伎をリメイクしてきた)にはそれぞれ「なぜこのように作り変えたのか」という意味が見いだせた。『勧進帳』(演出:杉原邦⽣)は「安宅の関=ボーダー」と見立て、国境、人種、性別、そういった様々なボーダーを「乗り越えられるか」という命題を掲げた大変すばらしい(そして面白い)作品だった。『義経千本桜ー渡海屋・大物浦ー』(演出:多田淳之介)は、争いという負の連鎖について考えさせられた。鳴り響くサイレンと赤いライトに照らされて立ちすくんでいる俳優の姿に、「戦いで一番つらいのは死ぬこともできず生きることもできない時間、いつ終わるとも知れない生殺しの時間が長く長く続くこと、なのかもしれない」と感じた。『桜姫東文章』(脚本・演出:岡田利規)は上述したように、歌舞伎作品そのものを客観的に批判的に見るメタレベルの構成だった。だが本作には、膝を打つような「今、この時代に、リメイクする意義」がない。スペクタクル性はあり情感たっぷりだが、それは歌舞伎を現代風に描きなおしたに過ぎない。
再演も3度目らしく、きっと評判は上々なのだろう。…だが、私が木ノ下歌舞伎に求めるものはこれではない。
見たいのは「現代の歌舞伎」ではない。「歌舞伎演目を使って描く現代」なのだ。
2023.07.18
カテゴリー:
2023年7月1日(日)13:00 @NIYOL COFEE

●非・売れ線系ビーナス 『些細なうた』
短歌:笹井宏之
脚本:内田龍太郎/田坂哲郎/村岡勇輔
演出:木村佳南子
出演:あだな・青野大輔・田坂哲郎・にしむらまなみ・ハットリユウ(LIGHTHOUSE CAMP CIRCLE)・やわらあさ(演劇関係いすと校舎)
音声出演:長野哲也
(*上記の情報は7/1 13時の回)
驚いた。
『些細なうた』は、笹井宏之という早逝した才能ある歌人と、その短歌を描いた作品である。手がけた田坂哲郎(作家・本劇団主宰)は同名のラジオドラマ(2011年、NHK佐賀局制作/NHKオーディオドラマ選奨佳作受賞)から始め、2013年に舞台化、その後10年に亘って本作を大事にしてきた。といっても、愛でるように撫でるように手を加え、作品はどんどんと形が変わっている。2013年の初演と2017年の再演を見ているが(再演も初演と違っていた)、2023年度版の今作はそのどちらとも全く異なる、元を換骨奪胎した作品になっていて、かなり驚いた。
ハッキリ言えば、これはほぼ芝居ではない。50分の公演を一日に4回(を二日間)、それぞれ内容を変えていた点も含め「パフォーマンス」と言える。(ステージごとに違うようなので、以下、この文章は私が見た7月1日(土)13時の公演に限定したものである)
帰りながら考えた、田坂は今作で何を描きたかったのかと。過去に見た2回の『些細なうた』との大きな違いは、「笹井宏之の物語」がないということ。今作が目指したのは「笹井宏之の短歌」を描くことだったのではないか。それは過去作のように「笹井宏之を描くことで笹井短歌を味わう」という手法でもなく、あるいは「田坂による笹井短歌の解釈を芝居にする」のでもない、「笹井短歌を生(き)のままで味わってもらう」試み。
そう考えると、なるほどと合点がいく。例えば、観客に短歌を声に出して詠ませる行為。1首を3つに区切り、同じく3つに区切った観客にそれぞれ暗誦させる。それも役者の指示に従って、ランダムに声が重複する形で、短歌を暗誦し合うのだ。これは短歌・言葉を意味ではなく「音」で楽しんでもらうという行為なのだろう。(『カエルの歌』の輪唱において「ケロケロケロケロ…」と音を転がすことが楽しくなってくるように!)
また、短歌とイメージを結ぶゲームも、短歌を味わうために用意された一つだろう。4枚の写真を並べその中の1枚をイメージした短歌を田坂が詠み、観客はどれがその写真なのかを当てるというものだ。これは正解当てゲームではなく、むしろ(短歌も適当に開いたページから選ばれるし、観客の選択したものに偏りがないことからも)喚起するイメージは無限で自由でいいのだと示唆している。
天井に貼られた短歌の紙片を観客ひとりひとりに渡してくれるのも、まるでその人に合ったものを吟味して選んでいるかに見えて、嬉しい。手にした一首が特別な一首に見えてくるから不思議だ。そんなこんなもすべて、笹井短歌を味わってもらうための仕掛けなのだろう。
田坂は「言葉」の作家だ。物語や人物造形よりも、言葉に重きを置く作家だ。この言葉を味わう試みが、カフェの地下、穴蔵のような小さな部屋で行われたことは意味があったと今さらに思う。閉ざされた空間だからこそ、言葉の感触がつかめるような気がするからだ。そして同時に、ひょっとしたらこの穴蔵は、生前の笹井の頭の中なのかもしれないと思う。その意味では、やっぱり、今作も「笹井宏之を」描いていたともいえるのかもしれない。
追記。所要時間50分のこの公演でチケット代3000円というのは正直なところ、高いと思う。各回異なる内容で見比べて見たかったが、その気になれない金額だ(2公演で5500円と少し割引にはなったようだが)。内容に見合う金額だったかというと疑問が残る。
2023.07.10
カテゴリー:
2023年6月18日(日)18;00 @箱崎水族館喫茶室

●プリマ・マテリア vol.15 「春と修羅」
おどり: 峰尾かおり
声とことば: いしだま
(はみだす朗読ユニットテクテクハニカム)
即興音奏: prima materia(プリマ・マテリア)
花田コウキ + 渡辺ハンキン浩二
照明:出田浩志(大屋屋)
言葉と彼女と内なる声が、シンクロしている気がした。宮沢賢治の言葉の断片と、峰尾かおりの存在と、私の奥から聞こえる声の、シンクロである。
――「わたくしといふ現象は」――風や光や水や時や、それらと同じ森羅万象の現象としての私が
――「せはしくせはしく明滅しながら」――たゆたい、まざりあい、ゆっくりと呼吸をしながら
――「一つの青い照明です」――ひっそりと、あるいはほんのりと、存在している、ような。
プリマ・マテリアvol.15の『春と修羅』である。宮沢賢治の詩の朗読(いしだま・はみだす朗読ユニットテクテクハニカム)と、ギターとドラムの即興の音(prima materia=花田コウキ+渡辺ハンキン浩二)と、その中での精気に満ちたおどり(峰尾かおり)。濃密な空間と時間に溶け込むような錯覚を覚える公演だった。

峰尾は、彼女の『春と修羅』を(つまりは彼女が理解した宮沢賢治の詩を)饒舌におどりで体現する。冒頭のかなり長い時間の緩慢な動きは「空間と時間との一体化」であり、森羅万象の一部であることを表わしている。それがステージに上がる頃には、人が持つ心の動き(例えば喜怒哀楽といった単純なものに分類できない多くの心の機微)ですらもこの世の自然だと体で詠う。豊かにたっぷりと、おどりが「語って」いる。そしてprima materiaの即興音奏は、存在感ある演奏でありながら同時に峰尾のおどりを後押しするサポート感もあり、バランスがよく感じられる。心地よい。

私にとって残念だったのは、朗読の強さだ。いしだまの声が特徴的であるからだろうか、彼女が声高に叫んだり、声色を使ったり、その激しさが耳障りに感じた。朗読の強弱に意味があったようには感じられず、却って邪魔をしているとすら思えた。ただ、面白くなったのは後半、彼女の朗読の声が「音」になってから。朗読としての意識が消え、言葉が音になってくると、ギターやドラムの音の上で転がっているようなイメージも喚起され、おどりと一体化していったように思う。


衣装についても触れておきたい。峰尾といしだまの衣装の柄は揃いで、どうやら着物をといて作った衣装ではないだろうか。特に峰尾の衣装は、細い帯状の布を、上半身は巻くようにして、下半身はプリーツのように並べてつなぎ、動きによって違う表情を見せる。おどる峰尾の四肢を魅力的に見せていた。動きやすさと見映えを兼ねた印象的な衣装だった。
明かりが戻り、拍手が起こり、演者の緊張が解け、空気が変わった。溶け合っていたものが「個」に戻り、公演は終わった。
2023.07.01
カテゴリー:

- 2026年1月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 『証明』Level 19
- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇
- 『きらめく星座』こまつ座
- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ
- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi
- 『受胎の森』ゴブノタマシイ
- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house
- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス
- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議
- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●
大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。
2005年~朝日新聞に劇評を執筆
2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆
舞台、映画、読書をこよなく愛しております。
演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。
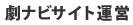
「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。
株式会社シアターネットプロジェクト
https://theaternet.co.jp
〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204