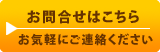2023年10月22日(日)14:00~ @山口情報芸術センター スタジオA

●『勧進帳』木ノ下歌舞伎
監修・補綴:木ノ下裕一
演出・美術:杉原邦生(KUNIO)
出演:リー5世、坂口涼太郎、高山のえみ、岡野康弘、亀島一穂、重岡漠、大柿友哉
スウィング:佐藤俊彦、大知
音楽:Taichi Kaneko
照明:髙田政義
音響:星野大輔
衣装:岡村春輝
振付:北尾亘
演出助手:鈴木美波
舞台監督:大鹿展明
ラップ指導:板橋駿谷
歌唱指導:都乃
鳴物指導:田中傳一郎
2016年に北九州芸術劇場で本作を見て以来、私にとって木ノ下歌舞伎は「見逃したくない」存在の一つになった。それから見てきた5演目のうちでもやはり本作が私にとってベストである。何度も見たいと思う舞台がそうそうあるわけではない中で、本作はもう一度見たいと強く思っていた。

7年ぶりの本作との再会は、YCAM(山口市)にて。劇場の力(吸引力)だろうか、ふらりとやってきて当日券を買う人が結構いることに驚く。壁には木ノ下裕一氏による、「作品の味わい方別・座席位置」が貼りだされていて(こういうの、初めて見た!)面白い。まずは一列目に座ってみるが目線が役者の足の位置だったので、やっぱり俯瞰的に見たいと3列目中央に座りなおす。前回見た時にライティングの妙にも心を奪われていて、そして何より終盤に出てくる光によるボーダーライン(本作の肝である)を再度見届けたく、少し上から見たかったのだ。
本作は歌舞伎『勧進帳』を現代劇に作り変えたものである。実兄・頼朝に追われた義経一行は、山伏の格好をして奥州へと向かう最中に安宅関で関守の富樫左衛門に止められる。すでに頼朝の命で「義経が山伏に化けていること、捉えるように」との命令が下っていたのだ。越えたい義経らと防ぎたい富樫の、必死の攻防があらすじである。それをベースに木ノ下裕一の監修・補綴、杉原邦生の演出と美術で、歌舞伎とは似て非なる物に生まれ変わらせたのが、本作である。
7年前に見た時の話から書こう。何よりも私が素晴らしいと感じたのは、「安宅関を越える」という物語を、「境界線を越える」というテーマで描きなおしている点である。弁慶役をアメリカ人のリー5世、そして義経役はニューハーフを自称する高山のえみが演じ、まずはこれだけでも演出の意図が分かりやすく伝わる。そうしてみると、従者であるはずの弁慶が(たとえ助けるためであっても)主人の義経を打つ姿も主従関係を「越える」ことなのかと、歌舞伎では考えもしなかったことに気づく。
越えることの難しさ。中世において「越える」ことの難しさは言うまでもないが、では現代は簡単なのか。国境も性別も上下関係も「たやすく越えられる、越えている」ように見えるが、それは幻想ではないのかと突きつける。前回の観劇で最も感じ入ったのはこの点だった。ライトによる一本の線・ボーダーラインが舞台に現れた時、それをはさんで義経が手をのばしている姿を見た時、ゾワっと何とも形容しがたい感動と複雑な思いに包まれたのが忘れられない。
もう一点、歌舞伎とは違う富樫の描かれ方も興味深いと思っていた。歌舞伎では富樫は「弁慶の主人を思う気持ちに打たれた、物の分かる男(?)」だ。弁慶もまた富樫が見抜いていることを分かった上で芝居を続ける。適切な比喩ではないかもしれないが、私のイメージではいつも「実力あるライバル同士が反目しながらも互いの実力を認め合っている。そこには実は妙な信頼関係もある。…というスポーツ漫画の主人公とライバル」を思いうかべてしまう。弁慶と富樫のあいだに生まれたものは、友情、人情、で片付けられる。ところが本作での富樫はそんな単純ではなく人間臭い。義経一行の固い主従関をまぶしく見つめ、自らを孤独に思い、関守とは名ばかりの殺人の虚しさを感じ、主従関係に縛られた自分(言ってみたら彼は中間管理職だ)と突き進む彼らの自由さに頼もしさとうらやましさを感じ、あるいは自分をも託した気になったのかも…こんな富樫を見たことがなく、衝撃的だった。
つまり「ボーダーという視点」「富樫の内面を描いた点」、この二点のすばらしさに私は圧倒されていた。

さて今回の公演で新たに感じたことを付け加えたい。それは2023年という今だからこそ感じた変化である。
4人の家来/番卒を演じる役者は、幕府・頼朝(富樫)側、義経側と立場を変えて二役演じる。走り回って大変な役なのだが、この「わずかな移動と場所の違いで立場が変わる」ことについて、ウクライナとロシアの戦争が重なったのである。本作は、彼ら一人一人のそれぞれ個性(気弱、すぐにカッとなるなど)が立場を変えてもそのまま演じられている。個性を継続させ同一の人間ともとれる描き方をすることで、「その男は、常陸坊海尊でもありえたし、番卒オカノでもありえたのだ」(その二役を岡野康弘が演じている)と気づかせる。つまりは、「所属なんて成り行きなのだ。住んでいる場所があちらだったら、今頃はあちらの人間として戦っている」ということ。帰属意識は本人のアイデンティティー確立に大切なものではあるが、しかし所詮は偶然や運によることも多い。と同時に、「運」で片付けるにはその末路の違いは残酷である。そのことが、今なお続くウクライナとロシアの人々と重なった。
また、「ボーダーライン」を概念的にラインとしてとらえていた前回の鑑賞だったが、それが「壁」として立ちはだかっているように見えてきた違いもある。それはコロナを体験したからだろうか(当日配布のパンフにも書かれていたが、トランプ前大統領がメキシコ国境に建てようとした壁も確かにイメージとしてダブって見えた)、ラインなら「越える」ことが可能にも思えるがそれが壁となるとはるかに難しくなる。…ひょっとしたら、長方形の舞台の短辺部分に照明機材の壁があったから、という単純な理由かもしれない(前回はその部分の記憶がない)。なんであれ、私には富樫たちが見つめる前方のその先に、壁が見えていたのだ。
単に「違う」と線を引くだけではない、相手を拒絶する、否定する、入らせない、壁。コロナ以降、他者とのつながり方が変わってしまい、私たちはその「壁」をどう越えることができるのかと途方に暮れている。壁を前にして言葉をつぶやいているだけなのか、富樫のように心を通わせ壁を取り払う存在がいるのか、弁慶たちのように壁の向こうに違う世界があるとつらくとも進んでいけるのか。後からそんな思いが浮かんできた。これもまた、2016年では感じえなかった新たな感慨である。
本作はずば抜けて完成度が高い。それでも次に見る時には、想像もしない新しい見え方を提供してくれるだろうか。それもまた楽しみである。

追記。弁慶は和歌山の出だから関西弁っぽい話し方なのかとか、富樫が持ってくるお酒が「天狗舞」だったことに安宅は石川だったなとニンマリしたとか、ピクニックシートをあえてレインボーカラーにしているのねーとか、そんな小ネタ(?)も楽しく見た。ラジオの使い方もうまいなぁ。そしてやっぱり計算されたライティングに、今回も鳥肌が立った。
2023.10.23
カテゴリー:
2023年9月3日(日)13:30 @久留米シティプラザ Cボックス

●『イミグレ怪談』
岡崎藝術座
作・演出:神里雄大
出演:上門みき、大村わたる、ビアトリス・サノ、松井周
●幽霊は空間と時間を移動する
「イミグレ怪談」=イミグレーション(immigration、移民)のこわい話。これは、移動する幽霊たちの物語である。
ふと、幽霊はどこで生まれるのだろうと考えた。古戦場で、墓地で、無念の死を遂げた場所で、彼らは徘徊したり佇んでいたりしていると聞く(幸か不幸か私は見たことがない)。つまり幽霊はいつも土地と結びついていて、土地の記憶を呼び起こす物語――「かつてその地で起こった」「そこには○○があった」という語り――の中から生まれてきた。
では幽霊は遠く離れた地に移動することができるのか。幽霊たちが旅し、土地に縛られず軽やかに動く姿を想像するとユーモラスではある。が、移民の歴史が決して明るく楽し気な話ばかりではないことを思うと、移民の幽霊が姿を現すのなら、彼らの言葉、そして彼らが語りえない言葉にも耳を傾ける必要があるだろう。もっとも、本作に登場する移民の話は、一様ではない。日本から南米ボリビアに渡った半世紀以上前の移民の話もあれば、現代の移民の話もある。空間(国境)を横断する移民の話を、時間を縦断する形で描いているわけだ(なるほど幽霊にしかできない技だ)。本作は、3人の幽霊たちが語り部となって「故郷を離れ、遠い土地で生きていく」話を繰り広げていく。
●「沖縄」の持つ記憶
舞台は四部構成だ。三名の役者が松井周、上門みき、大村わたるという本名のまま登場する。同窓会だと言って現れた割には、彼らは互いを知っているのかいないのか会話はかみ合わず、茫洋とした空気が流れている。関係が見えないまま、それぞれが一幕ずつ中心となって語りを展開する。
第一幕「タイの幽霊」は、酒好きが高じルーツをたどるうちに、沖縄を経てタイに住むようになった男・松井周の話だ。彼は沖縄のお酒・泡盛がタイ米で作られていること、そしてラオスの蒸留酒「ラオラオ」がルーツだと知り、新たにその蒸留酒に名前を付け沖縄で売り出していると語る。
第二幕「ボリビアの幽霊」は、上門みきがブラジルに住むハトコとオンラインで「ボリビアに移住した祖父の兄」の年金手続きについてやり取りをする中で、沖縄からボリビアへの移民の歴史について語る。上門の口から南米への移民の歴史の辛苦のみならず、なぜ沖縄からボリビアだったのかが語られ、合い間に無邪気にも大村が疑問をはさむ形で「ポルトガル人がブラジルにやってくる前にも住んでいる人はいた」ことや「移住後の国籍」について触れられる。ハトコとのオンライン映像がフリーズしたり上門と大村のやり取りが軽めだったりすることもあって、語られる内容の重さに比して明るめのトーンである。
第三幕「沖縄の幽霊」は、本州から沖縄に移住した男の話を大村わたるが語る。引っ越した先で出会った「マコさん」の話は後述するとして、興味深いことにここでは沖縄という地と幽霊の関係が語られる。いわく、沖縄では幽霊も妖怪も日常生活に溶け込んで共存している、国際通りを歩く人の3分の1が幽霊と言われている、沖縄戦で死んだ日本兵の幽霊が多すぎる、などと。
お分かりのように三幕まで沖縄が共通して登場する。かつては琉球と呼ばれた別の国だったということ(一幕)、日本が戦争に負けた後、アメリカ軍に占領され基地だらけにされ困窮したこと、見かねた沖縄出身のボリビア移民がボリビアにオキナワ移住地を作ったこと(二幕)。断片ではあるが沖縄の歴史を垣間見ると、三幕で沖縄では幽霊が共存しているというのは当然かもしれないと思う。先に述べたように、幽霊は土地の記憶を呼び起こす物語の中で生まれる存在なのだから。そして、この国はいまだ沖縄に負を押し付けている。本作は移動の物語の一方で、土地(沖縄)が持つ記憶を刻んでいる。
●「わかる」ということ。「わかっている」のは誰なのか。
さて四幕では、3人が集まって酒を酌み交わしている。上門は赤地に黄色の模様が入った浴衣を羽織っているのだが、これは三幕目の「マコさん」の恰好である。マコさんは沖縄に移住した大村の隣に住む女性で、彼に沖縄の妖怪の話をする。捉えどころのない存在なのだが、大村に向かっての言葉がいちいち示唆に富んでいる。例えば「あなたはわかっているようでわかっていないね」「あなたには歴史と呼べるものがない」「背負うものがない」。大村は何が分かっていないというのか、いやそもそもここでいう「あなた」とは誰のことなのか。
ここで注目したいのが大村の恰好で、実は一幕目から不思議なつなぎ服を着ている。四幕目で彼がそれを脱ぐと、なんとオムツ姿。つまりつなぎ服はロンパースで、彼は「赤ん坊」ではないか(シアターカフェの参加者の意見。なるほどと頷いた)、しかしなぜ赤ん坊なのか。
考えるにこれは、赤ん坊のように「何も知らず排泄物も処理してもらえ、きれいな状態でいる者」の象徴なのではないか。いや、赤ん坊は大きくなり、やがて自分の始末は自分でつける。無垢で未来のある赤ん坊の比喩というより、誰かに沖縄の後処理を押し付けて、過去を見ることもなく能天気に歴史や現実を見ていない、見ようとしない、「わかっていない」我々のことを指しているのではいだろうか。
翻ってマコさんとは誰なのか。実は3人の役者の中で上門だけが沖縄のイントネーションで喋っている。マコさんが、自分を「過去に囚われて殺され続ける存在」と言うくだりがあるが、つまり彼女こそが「沖縄」なのだろう。印象に残っている言葉がある。酒を飲みながら上門が「(魚の)目玉が一番おいしい、二番目が骨、三番目が皮だ」と言った後に、「肉体よりも骨よりも、何を見てきたかってことだよ」とつぶやくのだ。――沖縄は見続けてきたのだ、そこで何が起こったのか、行われてきたのか、どうしてそういう事になっていったのかを。私たちは見続けてきたか。目をそらしていないか。分かった気になっていないか。恥ずかしい思いと共に自問する。
舞台中央にある、天上に続く黒い帯(道)の上で3人の幽霊たちはそれぞれの好きな酒を飲んでいる。…お酒なら、どこがルーツであろうが、どの国境を越えようが、誰も気にしないのに。私たちが歴史から目を背けなければ、誰に何を強いることなく、軽々と「越える」ことができる日が来るかもしれない。星空の下の3人を見ながら、それが今を生きる私たちの課題なのだと思った。
2023.10.18
カテゴリー:
2023年9月18日(月)13:00 @甘棠館Show劇場

●『畜生達のエデン』
マジカル超DXランド
作・演出:そめやみつ
出演:溝越そら、风月、沢見さわ、池田千春、松永檀、薔薇園花江
一時代前の匂いのする作品である。貶めているわけではない。チラシが醸し出す雰囲気といい、昭和の漫画風な物語といい、役者の演技といい、時代がかっているという点で統一感があり、振り切れている印象で面白かったのだ。若い人たちにも新鮮に映ったかもしれない。
鉄琴で演奏しているのだろうか、『むすんでひらいて』の曲が流れる中、舞台が始まる。目の粗い網が、客席と舞台のあいだを隔てている。受付も不織布の手術服っぽいものを着ていたし、不穏な雰囲気が漂う。舞台は大学の医学部なのか、網の向こう(=客席側)にいる豚を捕まえて「のうじゅう(膿汁?)」とやらを採取する女たち。灰原研究室のメンバーだという。どうやらこの世には男という性がなく、採取した「のうじゅう」によってのみ人工授精で人間を生み出せているらしい。しかしその技術を持っているのは灰原教授のみ、他は理屈も分からず従っている。その作業をする3人(ユウ、サツキ、ジュン)の会話から、ユウとサツキが恋人同士であるということ、この世では妊婦の二人に一人が異常をきたしてしまい、ユウの母親・フジコもそうであること(精神病棟をぬけ出して徘徊している)がわかる。そして女だけの世界で唯一男の「天主様」がアイドル扱いされていた。そんな中、仕事のできないジュンのミスによって、灰原が隠していた秘密が明らかになっていく。
ネタバレをすれば、『むすんでひらいて』の曲によって洗脳され(?)男がすべて豚に見えてしまう、つまりは認識の歪みで男が豚にしか見えなかったというオチである。灰原研究室での施術は豚からではなく人の男からの人工授精に過ぎず、また妊婦の錯乱も産んだ子が豚に見えたことによるものだった。ユウの母親が「スグル!」と我が子の名を叫んで豚の檻に向かおうとするのもつじつまが合う。そしてこれらは全て、「天主様」の仕組んだことだった…。荒唐無稽ではあるが、破綻がなくこの世界を作り上げていて、その点でノンストレス。藤子・F・不二雄のブラックSFというか昭和の漫画に出てきそうな設定である。灰原ジャコ(薔薇園花江)や茶頭アスカ(池田千春)の演技も昭和的大仰さがあるが、本作にはぴったりで却って味になっている。
しかし、当日配布されたパンフレットに書かれた文章を見て、疑問が生まれる。「ジェンダーという言葉が注目され、多様な性を受け入れようとする活動の一方で反発する声もある、そのドロドロとした対立にやりきれなさを感じて、嫌悪から解放された楽園を作ろうと思って本作を作った」(注:要約)と書かれている。その意図で作られたのだとしたら、本作について単に「昭和的なドロドロ感が面白いわぁ」という調子ではいかなくなる。
なぜなら本作は単純な「男 vs 女」という二項対立の物語だからだ(それが昭和的な印象を与えている大きな要因だろう)。認知の歪みによって男の存在が消されてしまうというのは虚構(フィクション)としては面白いが、そのことによって新しい展開があったわけでも何か発見があったわけでもない。ましてやパンフに書かれている「ジェンダーの問題」は全く関係がない。むしろ警備員である茶頭アスカというキャラは「宝塚の男役」っぽくて、作られた男性像の誇張という意味で「男性性のステレオタイプを助長」していると言える。さらに言えば、現代は「生物学的性(セックス)と社会的ジェンダー」という二元論的な対立項で単純に語られることすら難しくなってきている。本作の単純さは一時代も二時代も前の感覚と言わざるを得ない。
「大真面目に受け取るなよー」と思われるだろうか? いや、「真面目すぎ」「めんどくさい」「わかりにくい」という言葉でいろんな社会的マイノリティの主張や声を封印してきたことを思うと、このことは無視してはいけない気がする。少なくともどこまで考えて作ったのか、社会での問題について理解が及んでいるのかは疑問視しておく必要があるだろう。この設定を「大真面目に」捉え、「めんどうでも、わかりにくくても」発展させれば、今回の荒唐無稽なフィクションではない、何かしらを投じる作品になる可能性もあったのではないかと残念な気持ちになった。
2023.10.14
カテゴリー:
2023年9月13日(水)13:00~ @大濠能楽堂

●『能 狂言 鬼滅の刃』
原作:吾峠呼世晴「鬼滅の刃」
主催:OFFICE OHTSUKI
監修:大槻文藏
演出・謡本補綴:野村萬斎
作詞:亀井広忠
原案台本:木ノ下裕一
出演:(シテ方)大槻文藏、大槻裕一、(狂言方)野村萬斎、野村裕基、野村太一郎、(ワキ方)福王和幸、福王知登 ほか
*『鬼滅の刃』の登場人物の漢字を正しく表記できません。「鬼舞辻無惨」の「辻」のしんにょうは点が一つ、「禰豆子」の「ね」はネ偏、「はがねづか」も漢字です。
台本を木ノ下裕一さんが手がけていると知り、そして漫画&アニメの作品をどう能狂言にするのだと興味を持って出かけた。歌舞伎では『風の谷のナウシカ』も『ワンピース』も見ているが(注:後から、『VR能 攻殻機動隊』を見たことを思いだした)、能 狂言の場合はもっと制約が多いはず。舞台装置も作りこむことはできないだろうし、セリフも難しくなるだろう(見慣れていない観客には、歌舞伎以上にわからないだろう。そして歌舞伎にはイヤホンガイドがあるが、能狂言にはイヤホンガイドはない、少なくとも私は見たことがない)。しかしチラシに書かれた「人も鬼 鬼も人」という文字に、実は『鬼滅の刃』は能 狂言化するのに最も適した作品なのだと気がついた。というのも能における鬼と、『鬼滅の刃』における鬼に共通点があると思ったからである。
能は五番立という上演形式から成っており、そのうちの最後の切能物は鬼が登場する演目である。ただ私が感じた『鬼滅の刃』との共通点の鬼とは、それよりも、愛する男性に裏切られた女性や嫉妬に狂う女性が変化(へんげ)した鬼(例えば四番目物の雑能の演目『葵上』では六条御息所の生霊が鬼となって現れる)の方。単なる異形の恐ろしい存在ではなく、「鬼と化してしまった(鬼にならざるを得なかった)人間」と考えた時に、その業や悲哀や辛さが立ち上がってくる。その存在の複雑さが、共通項だと考えたのだ。「鎮魂」、である。

さて始まってすぐに登場するのは鬼舞辻無惨(野村萬斎)。客席後部から現れ、青いライトと風の音(音は私の記憶が勝手に作り上げたかもしれない…)の中、気づくと彼は立っていた。客席と舞台の境界となる白州を超え、階(きざはし)を一歩一歩踏んで、能舞台に上がっていく。正面前から二列目に座っていた私だが、実は声を聞いても顔を見ても萬斎だとわからなかった。フッと「気づくとそこにいる」無惨の出現に度肝を抜かされたのだ。軽く感動を覚える。
一転して(囃子方が入ってその後の)新作儀礼『日の神』となる。五番立には必ず「翁」という祝祭儀礼から始まるそうだが、それに代わるものとしてのこの番組。炭治郎(大槻裕一)とその父・炭十郎のやりとりで、炭治郎が父からヒノカミ神楽を伝授されるという、物語の起点ともなるシーンである。竈門家が代々受け継いできた大事なヒノカミ神楽(舞)を、能においても格式高い「翁」に位置付けるという、あまりにぴったりの符合に膝を打つ。それにしても黒と緑の市松模様の衣裳を身に付けただけで炭治郎と分かるのだから、キャラクターは特徴的な衣裳を身に付けておくべきなのだなと変な所でも感心する。囃子方が「円舞、火車…」と謡うのも『鬼滅の刃』ファンにはたまらないかもしれない。
脇能『狭霧童子』も、「能にするために仕組まれていた」としか思えないほどの、ピッタリのエピソード。『殺生石』に出てくる大岩と炭治郎の修行のエピソードが上手く重なるのだ。単純に楽しんで見る。感心したのは修羅能『藤襲山』の手鬼の表現。複数の者が被り物をして手鬼を表現する。演劇の舞台では見慣れた感もあるが、能でもこういう表現はアリなのか。思った以上に能も自由があるのかと驚く。
鬘能の『白雪』も、夢幻能の形式を持つ能ならではのかたち。「鬼になった禰豆子の夢」として身の上が描かれる。『鬼滅の刃』の世界観を無理することなく能の形式に落とし込めていることに、ほとほと感心する。禰豆子が入っている箱がデフォルメされ大箱で登場し、彼女はそこから現れ、またその箱に戻っていく。こういった原作の特徴のおかげで通常の能にくらべてわかりやすく、でも能から外れていない点が見事である。その一方で雑能『君がため』はもう少し現代劇寄り?のラフさがあり、こういった振れ幅の大きさが本作の懐の深さ。善逸、伊之助、炭治郎のキャラクター(炭治郎の生真面目さが際立つ!)が見事に描かれていて、原作ファン向けに作ったかと勘ぐってしまう程だ。
途中に狂言は二つ入る。『刀鍛冶』は日輪刀を作るハガネヅカ蛍が刀を鍛錬しながら独り言つる様子がコミカルでホッとする。『鎹鴉』も伝令役を務める鎹鴉たちにターゲットを絞り、彼らのやり取りが面白い。お酒を飲んで苦労をぼやいて…。箸休めと言っては失礼かもしれないが、注目されるキャラクター達以外の視点から『鬼滅の刃』に焦点を当てているのも、本作の優れたところである。
見どころは最後の切能『累』。正直に言えば、クライマックスなのに内容が私は頭に入っていない。とにかくビジュアル的に目を奪われっぱなしだったからだ。『土蜘蛛』で何度も見た「手から繰り出される糸」がこれでもかこれでもかというほど炭治郎に向かって投げられ、炭治郎の持つ刀は糸が巻き付いてぐるぐる真っ白、舞台上も糸の残骸で埋め尽くされていて、圧巻。累(大槻文藏)、そして彼に対峙する炭治郎の距離が、糸によって狭まっていく。物理的空間が埋め尽くされていくようで息苦しく、緊迫感が高まる。そして赤い糸まで! 糸がシャーっと投げられ放物線を描いて落ちていく中で、累は美しく悲しく立っている。戦いを美しく表現することを良しとしたくないが、思わず口の中で「きれい…」とつぶやいてしまった。実は私が見た回ではちょっとしたハプニングがあったのだが、それでもこの番組の価値は全く損なわれていない。炭治郎に負けて…父、母と去っていく時の累の背中の小ささ…『鬼滅の刃』の世界観は、この物悲しさだなと思いだす。人であれ鬼であれ、生きるとは業が深いことなのだと累の背中が語っていた。
最後に、面の美しさについて触れておきたい。能面作家・島畑英之氏の作品だという。あまりにかわいらしく素敵で、ポストカードを買わずにはいられなかった。



2023.10.03
カテゴリー:
2023年8月13日(日)13:30 @久留米シティプラザ 久留米座

●KAATキッズ・プログラム『さいごの一つ前』
作・演出:松井周
出演:白石加代子、久保井研、薬丸翔、湯川ひな
1.
これは記憶の旅なのか。
死んでしまった3人と彼らの案内人が、椅子の船に乗ってほの暗い「何もない空間」を進んでいく姿に、涙が出てきた。そうか、人は死んだ後、記憶の旅に出るのか。折しも公演日がお盆だったからだろうか、私は大事な亡き人を思い出しながら、これは記憶の旅の物語なのだと思った。
死んだミチロウ・マリン・カオルが「地獄の案内人」を名乗るアキオに連れられて、地獄あるいは天国へと案内されるその道中を描いた作品だ。最近は天国もいっぱいで何とかして3人を地獄に連れて行きたい案内人アキオ。天国に入るには「その人にとっての最高の思い出」が必要なのだと言う。生前、ビジネスで成功した(その名は誰もが知っている)ミチロウは自分こそは天国に行くべきだと主張する。先に死んだ父親が待っていると地獄に行きたがるマリン。そしてカオルは自分の名前すらも忘れ、時折思い出す断片もあやふやなもの。「何もない」空間を進んでいく彼らはやがてそれぞれの場所へと移動していく――ミチロウは、孤独を知り壮大な自然を感じた学生時代のささやかな思い出によって天国に行くことができ、マリンは悪人になりきれなかった自分を思い出すと同時に現世の病院で目が覚めて生き返っていく。そして残されたカオルは…
本作の一つの肝は「記憶」。生きているということは記憶の積み重ねである。私が生きた証は幻のごとく形はないけれど、記憶があるから「私」で在り続けられる。支えや励みになる幸せな記憶もある一方で、まとわりついて離れない悔恨や苦悩というつらい記憶もある。でもそれらを積み重ねて「私」が成り立っている。死んだはずのミチロウやマリンが、生きていたときの記憶に縛られているのもその裏返しであるし、また、だから天国に入るのに「その人の持つ最高の思い出」が必要なのだ。
それは故人についても同じだ。生身の身体はなくなっても、私たちは亡くなった人のことを偲び、思い出し、懐かしむ。物でも匂いでも場所でも、様々なきっかけで記憶が呼び起こされ、その瞬間、その故人は生きている。私が彼らの旅に涙したのは、記憶という儚いものを大切に大切にしている私たち人間が健気で愛おしいと感じたからだろう。
ところが興味深いことに、白石加代子演じるカオルは記憶がない。自分のことすら分からない。時折ポロポロとあやふやな記憶の断片がこぼれ出てくる。認知症を連想させるが、でも圧倒的に違うのは認知症が「本人が忘れても周りはその人についての記憶がある」のに対して、カオルには彼女のことを知る人がそこにはいないということ。屈託ない彼女がかわいらしくてつい忘れそうになるが、本来ならそれはとても怖いことではなかろうか。私が私を覚えていない、そして私のことを知る人もいない。なんとも出口のないゾッとする話である。果たしてこの話の行き着く先はというと、なんと彼女が有名な女優であることに地獄の案内人アキオが気づくというものだった。アキオは、地獄ではなく現世で幽霊となる「さいごの一つ前」の道を教え、女優のあなたなら誰かに思い出してもらえる、そうしたらもう一度ここに戻ってくるチャンスがあるのだと伝える。
彼女が有名な女優だから思い出してくれる人もいる…? 正直に言えばこの結末に落胆した。有名でなかったら思い出してもらえないというのだろうか。それではあまりにも救いのない話ではないか。
記憶の中に自分の軌跡があるということ。そして仮にその人が亡くなってもその人自身が忘れたとしても、周りがその人の事を記憶している限り在りし日のその人は生きている。あなたの生きた証は、あなたとあなたの周りの記憶の中にあるのだ。だから、どんな人であっても必ず、あなたを記憶している人(言い換えるとあなたを大切に思っている人)がいるはずーーこの展開なら納得がいくし、老いや死をむやみに忌避せずに誰にとっても受け入れられる話になったと思うのだが、女優だからという特殊な理由にしたことで、あくまでも「カオルの」物語になってしまった。最後の最後でいきなり自分の物語とはかけ離れてしまった。残念である。

2.
もう一つ考えた事がある。「生/死」を扱う芝居において、舞台という虚構を破って観客という現実と繋がる試みの相性の良さだ。本作ではカオルたちが「透明幕の向こうに誰かがいる」と気づき(それは観客のことである)語りかけ、観客と意思疎通を図るシーンがたびたび登場する。観客は拍手や足踏みで応じたり、時には子どもが答えを口にしたり、観客としてではなく「作品の一部として」参加することを求められる。子ども向け作品らしい、飽きさせない工夫の一つだ。
演劇はもともと虚構(フィクション)であることを前提に成り立つ芸術だ。観客が舞台上の虚構に同化するような作法にせよ、観客が舞台上の虚構と一定の距離を保つ異化を狙った作法にせよ、眼前の舞台を「見る」という行為で成り立たせている。多くの劇作家たちが、舞台と観客の関係の在り方を意識的に考えてきた。昨今では観客参加型の演劇(イマーシブシアター)も増えてきている。そんな議論をしなくても、幼児向けの芝居では昔から観客に協力を求め(悪役をたおすのにみんなの声援が必要だ!)舞台の外にいる観客を虚構に「引っ張りこむ」ことをしてきた。
翻って舞台で死後の世界を描くことは、太古の昔からある死後の世界を想像し見たいという欲望の構図と同じ。そして私たちは、恐山のイタコとまではいかなくても夢に故人が出てくれば何らかのメッセージだと受け取ったり、死後の世界から生還した話に興味を持ったりと、死の世界と現実を結ぶことになじみがあり、そのアクセスがあればいいのにとすら思っている。従って、「死んだカオルたちと現世が何らかの形で繋がっている」ことがすんなりと受け入れられるし、その上やり取りができるんだったら願ってもない。「客席/舞台」の関係をそのまま「生/死」に置き換え両者を結ぶ手法は、なるほど相性がいい。(だからマリン役の湯川ひなが観客に語り掛ける時に「幼児番組のおねえさん」のようにならずマリンのままでいてほしかった)
それにしても、ありえない状況を「さもありなん」と思わせてしまう、白石加代子の存在の説得力よ。時間のない空間にいることに違和感がないし、彼女ならお腹から宇宙を生み出してもおかしくないと思わせる。何かを超越した存在と言おうか、安易な言葉で片付けたくないが、特異な存在感としか言いようがない。(ミチロウもマリンもアキオも、こういうタイプの人は周りにいると思うが、白石加代子のカオルだけは、いない。)「さいごの一つ前」に戻ることができるのは、やっぱり彼女のような人に限られるのだろうなぁ…(納得)。

2023.10.03
カテゴリー:

- 2026年1月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 『証明』Level 19
- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇
- 『きらめく星座』こまつ座
- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ
- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi
- 『受胎の森』ゴブノタマシイ
- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house
- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス
- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議
- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●
大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。
2005年~朝日新聞に劇評を執筆
2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆
舞台、映画、読書をこよなく愛しております。
演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。
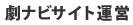
「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。
株式会社シアターネットプロジェクト
https://theaternet.co.jp
〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204