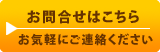2023年11月18日(土) @リノベーションミュージアム冷泉荘

●『OTONA HAHHA-!! START』HAっHHA-!!
統括:もりたかし
演出:後藤香(劇団 go to)
『スパイス・イン・ザ・バスケット』
作:三島ゆき
出演:水谷文香、梶川竜也
『結婚相談所』
作:サタケミキオ
出演:角野優子(劇団96文字)、川嵜圭太
『兄への伝言』
作:蓬莱竜太
出演:清水さなえ、本多陽彦
照明:桑野友里
音響:森貴史
舞台監督:梶川竜也・本多陽彦
舞台装置:中島信和(兄弟船)
映像:宮崎亮
制作:清水さなえ、大財靖子、高木怜奈、天野茜、やっひー、山口和彦、HAっHA-!!
30分の短編が3本。パンフによれば、2005年にパルコプロデュースで上演された『LOVE30』シリーズの1作目だという。三島ゆき、サタケミキオ、蓬莱竜太の戯曲は、大人の男女の恋愛を描いている。10代20代前半の若者から見たら「大人の恋愛は酸いも甘いも分かっている」と思うかもしれない。まるで恋愛でジタバタするのは若者の特権であるかのように。でも現実にはいい年した大人だって、未練を引きずったり、何でもないふりをしたり(隠し通すこともできないことだってある)、オロオロと取り乱したりすることもある。
さて本上演は「男たちの物語」だと思った。それも、「それなりに年を重ねた男たち」の物語。もちろん女優陣の演技あってこそではあるが、男と女の恋愛というよりも、3本とも男たちの想いが人間臭く伝わる作品だったのだ。というのも、本作では男優たちがみっともないほどに人間的でカッコ悪い。(注:ほめてます)キラキラした若者ではない、年齢を重ねた普通の男たちの、不器用さが際立っていたからだ。
例えば1本目『スパイス・イン・ザ・バスケット』の梶川竜也(劇団風三等星)は、突如、現れた元妻(水谷文香)に引っ掻き回される役を演じる。奔放でわがままな元妻にさんざん振り回され右往左往するカッコ悪さ。ガツンと断れないのかと観客は苛立ちすら覚える。さらに、今からやって来る新しい恋人(恋人候補?)へのアプローチが、「私の時と全く同じ」と元妻に指摘されるカッコ悪さ。でもそんな様子を見ながら観客は、彼の中の妻への複雑な気持ち――自分を捨てたことへの恨みと今さら現れる苛立ちと翻弄される情けなさとくすぶる奥底にある想い――を受け止める。年齢を重ねた役者だけに、「別れても離れても、出会った人が自分の中に残っていくのだ」という言葉が(そして逆に「一緒にいても1人だ」という言葉も)しっくりくる。(作中では「元妻が僕の中に残っている」という限定的な表現だったけれど。)役者によってはコメディ要素が強くなる本作だが、『Time after time』の旋律と共に、私には彼の弱さと優しさという人間臭さが強く残った。
2本目の『結婚相談所』もバタバタしたコメディである。結婚相談所コンサルタントの女性と、電話での悩み相談の先生をする男性が、互いに想いながらすれ違う、少し切なさも漂う物語だ。これも肝となるのは悩み相談を受けるホリカワ役の川嵜圭太。相手アオヤマ役の門野優子(劇団96文字)がジタバタするのはコメディ定番の笑いを誘うが(早口がうますぎる)、川嵜は少し勝手が違う。結婚相談所にやって来るのに自分を曲げない姿は、役者が違えば「変わり者」として映るだろうが川嵜の場合は泰然自若と見える。落ち着いた声や大柄な体躯のせいだろうか。一方で女性慣れしていないという設定で、終盤にアオヤマに「つき合っちゃう?」と言ってしまう、そのタイミングの悪さとか言葉のチョイスの悪さとか逃げを用意するような態度とか…が、「いかにも」なカッコ悪さなのだ。そして彼がこだわるデートに理由があったことが分かるラストには、不器用な男の純情を感じずにはいられない。それもこれもカッコ悪さがあってこそ引き立つ純情である。
3本目の『兄への伝言』は、男の未練がましさと女の潔さが際立つ作品だ。亡くなった弟の弔問で、弟の妻でありかつての想い人だった幼馴染に会う男。その昔トンカツの大きさで彼女に告白する賭けをした兄弟は、二十年近く経ってもそのことが大きく引っ掛かっていた。弟は死ぬ間際に「トンカツトリカエタ」というメッセージを残すほどに、そして兄弟二人ともそれ以後トンカツを食べずにいるほどに。男たち二人はその時から時間が止まったままなのだ。それに対して、すべてを打ち明けられた女のサバサバとした様子が印象的。トンカツを取り替えたのは(何も知らなかった)自分だった、この地を出ていきたかったけれどこの人生を選んだのは自分だと明るく強く答える。
それにしてもこの男たちのナルシシズム(自己陶酔)にはため息が出る。告白さえすれば彼女を自分のものにできるという思い上がり、トンカツの大きさごときで物事を決定してしまう浅慮、長きに亘って前に進めない成長のなさ、そして今なお彼女を誘う自分本位な考え…「男は、女は」という乱暴な言い方はしたくないが、これらを昔から「男のロマンティシズム」とでも称していたのかもしれない。
しかし、本多陽彦のなんだか湿度ある演技はロマンティシズムもナルシシズムも無縁で、ただただ思い込みの激しい未熟な男なのかもしれないと思わせる。対する清水さなえが「根から明るく同時に現実を見据えている大人の女性」を演じているおかげもある。前2作の愛すべきカッコ悪さとは違うが、大人になり切れていない男のカッコ悪さと言えるのかもしれない。
あがいて悶えて、自信過剰でいながら自信がない、等身大の男たちの物語。演出の後藤香がそれを意図したのかわからないが、リアルな男たちの人間臭さが際立つ面白い3本になっていた。
2023.12.13
カテゴリー:
2023年11月12日(日) @広島市東区民文化センター スタジオ2

●『遺食』 INAGO-DXイナゴデラックス
原作:オギエ博覧会『バラと肉』
脚本:武田宜裕×山川愛美
演出:武田宜裕
出演:武田宜裕、山川愛美、山田健太、市原真優、西村慎太郎(劇団Tempo)
声の出演:三浦雨々、青山正幸、江角昌美、江角幸記、江角幸真
スタッフ:舞台美術:奈地田愛
照明:佐々木隆良((株)篠本照明)
音響:川崎久司、岸本夏芽
衣裳:中川綾子、三浦有美
小道具:武田美由紀、江角昌美
舞台監督:池田典弘
宣伝美術:北木悠里(グンジョーブタイ)
映像:下前田碧
スチール:石井清一郎
映像記録:すえたけタイキ
当日運営:北木悠里、佐々木敦子、宮川愉可
制作協力:佐々木敦子
制作:宮川愉可
「死んだら何味になりたい?」という強烈なコピー。「遺食」という聞き慣れない、そして一気にいろんなイメージが押し寄せてくる文字。チラシに衝撃を受けて、広島まで出かけることにした。
「故人の遺志を受け継ぐ」ために、遺族は遺体の一部を「相続」して食すことが努力義務化された近未来の話。ぶっ飛んだ発想ではあるが、実は戦前の日本でも地域によっては火葬後の遺骨を噛む(場合によっては食べる)「骨噛み」という風習があった。また人肉を食すカニバリズムは空想上の話ではなく(まさがに劇中で本制度の発案者が文化人類学者という設定だったが)文化人類学の研究でその風習を持つ地域があったことが知られている。飢餓状態でのカニバリズムではない場合は、その行為には「継承」であれ「復讐」であれ「輪廻」であれ、社会的な意味がある。
その観点から言えば、本作は遺食制度が導入された理由に説得力が不足している。遺体を食することと「遺志を受け継ぐこと」が結びついていない(その説明がない)からだ。仮に遺食することが遺族にとって物理的に変化をもたらすとか、遺食しないと遺言がわからないとか(SFっぽい)、絶対的な愛情のバロメーターとなっていて食べないと世間体が悪いとか、突飛ではあるがそんな理由があれば納得する。だが本作には受け入れるにせよ拒否するにせよ、社会的にそうせざるを得ない理由が設定されていないのだ。またそうでないのなら、国が「努力義務化」するほどにこの制度を推し進めたい理由がなければならない。前提部分の説得力不足に引っ掛かりを覚えながら鑑賞する。
ところが、(通常なら物語の前提に説得力がないのは致命的なはずなのに)なかなかに印象に残る作品となったというのが面白い。まずは簡単にあらすじの紹介をしよう。故人の肉を相続して食べる法律が定められて数年、その生みの親ともいえる文化人類学者エイイチが亡くなった。エイイチの息子である公務員のエイゴ(武田宜裕)は父親の肉を遺食するのを拒むが、「遺食師」のイトウ(山田健太)が現れ、葬儀と同等の儀式として遺食の準備が進められていく。そんな中、エイゴは遺食師のイトウとエイゴの後妻・春花(山川愛美)のあいだに過去に何かがあったことに気づく…。
本作の面白さは「食べる」という行為と愛情を結び付けて見せる点だ。エイゴの娘モモが恋人にあれこれ手料理を食べさせてもらうこともそうだし、実の息子が拒否するエイイチの肉を春花は食べると言うこともそうだ(おかげでエイゴの後妻である春花はひょっとしてエイゴの父のエイイチのことが好きだったのかというフラグがかなり早くから立つ)。出色は学生時代から春花のことを想っていたイトウが春花に「食べていいよ」と言われ食べようと迫るシーン。「食べる」は性行為のメタファーとして浸透しているせいだろう、好意を寄せる女性を食べようと迫るイトウ、後ずさりしながらなすがままになる春花、この2人の姿の生々しいこと。特にイトウ役の山田の湿った感じと、春花役の山川のそそられるような魅力が相まって、ここで初めて「食べるほどに愛している」ということが腑に落ちる。これによって、ラストの泣きながらエイイチの右手をかじる春花のシーンが際立ち、彼女は勤めていた頃からずっとエイイチが好きだったのだと明らかになる。――死後に春花の誕生日だと花を贈ってきたエイイチ、しかも誕生日を間違えて…春花はそのことが分かった瞬間に泣きだし上述の衝動に駆られるのだが、エイイチは春花の気持ちに気づいていたのかもしれないとか、学者バカで気づかないままだったのかもしれないとか、登場しないエイイチとの関係まで観客が思いを巡らせるラストとなっている。終盤からラストにかけて密度が濃い。
欲を言えば、エイゴの「父親を拒絶する態度」をもう少し複雑に描けなかったか。文化人類学者のエイイチがフィールドワークに出かけ家庭を顧みないという理由を口にしていたが、実は春花の気持ちが父親にあることに心の奥底で気づいていた(自覚はしていないが)…エイゴをそんな風に描けていたらと惜しい気がする。その不足は台本のせいか、演技のせいか。
食と愛の禁断の関係を描いたが、子や孫を含む遺族による「遺食」の制度は少しそれとはズレがある。ある意味、遺食が制度化されている設定でなくても本作は成立するのかもしれない。とはいえインパクトも大きく勢いのある面白い作品だった。
追記:私は文化人類学者の妻です(笑)。
2023.12.03
カテゴリー:

- 2026年1月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 『証明』Level 19
- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇
- 『きらめく星座』こまつ座
- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ
- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi
- 『受胎の森』ゴブノタマシイ
- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house
- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス
- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議
- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●
大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。
2005年~朝日新聞に劇評を執筆
2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆
舞台、映画、読書をこよなく愛しております。
演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。
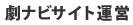
「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。
株式会社シアターネットプロジェクト
https://theaternet.co.jp
〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204