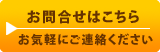2023年7月23日(日)13:00~ @J:COM北九州芸術劇場

●劇トツ×20分 2023 チャンピオン大会
@J:COM 北九州芸術劇場
参加劇団:劇団言霊(北九州)
F’s Company(長崎)
ブルーエゴナク(北九州)
劇団ヒロシ軍(長崎)
万能グローブガラパゴスダイナモス(福岡)
不思議少年(熊本)
PUYEY(福岡)
2012年から毎年楽しみにしていた「劇トツ×20分」が今年で終わるというのを知った。
――2000年代初頭、全国的に演劇バトルが増えていて、福岡でもE-1グランプリという演劇バトル・九州大会などが開かれていた。(他にももう一つあった記憶がある。不確かだが。)ただ、福岡は「笑わせたチームに票が入る」という傾向があって、観客投票システムの難しさを感じていた。「観客受けのいいもの(=わかりやすいもの)」だけを評価してしまうことに問題があるからだ。この問題については議論が尽きないので今日は書かないが、いずれにしても評価軸が「あるようでない(でもある)」という演劇バトルは難しい。北九州芸術劇場(現・J:COM北九州芸術劇場)の試みに、どうなることかと思いながら見始めたのを覚えている。そしてふたを開けてみると…「笑いだけに票が偏る」「元から人気の劇団が有利」「抽象的、分かりにくい作品は評価されない」「組織票が入る」といった問題は杞憂に終わり、実りの多い企画だったと思う。
理由はいくつかある。
①投票システムが練られていたこと。一人2票を持ち必ず2票とも入れる(1劇団につき投票は1票のみ)、審査員2名がそれぞれ30票ずつもっている、このやり方で上述のかなりの問題点は解消されていた。
②北九州芸術劇場ができて10年経つ頃に始まっており、観客が育ってきていたこと。観劇そのものを愛する土壌が育っていたために、「ひいき目ではなく優れたものを選びたい」という気持ちが充満していたように思う。
③新たな出会いの場になっていたこと。まず未知の劇団に出会う場になっていた。北九州で長崎や熊本の(他地域の)劇団の作品が見られるのは多くの観客にとって滅多にない機会だったし、劇団側にとっても同様に認知してもらう良い機会だっただろう。また制約(20分で3人以内の登場人物)が生み出すいつもと違う面白さに出会う場にもなっていた。制約が吉と出れば、劇団にとって新たな魅力の開拓になったし、観客にとってもそれが楽しみでもあった。
④審査員が豪華だったこと。覚えているだけでも永井愛さん(二兎社)柴幸男さん(劇団ままごと)前田司郎さん(五反田団)映画監督のタナダユキさん…プロとして活躍している(有名どころの)彼らが地方劇団のしかも短編作品に対して丁寧に講評してくれる(それを観客として聴ける)のも有難く面白く、それだけでも十分に価値があった。
⑤優勝賞品が「北九州芸術劇場での上演権」だったこと。なかなか手が届かない芸術劇場で公演が打てるのは劇団にとってステイタスである。もっとも、それによって金銭的に厳しくなったという問題もあったと聞くが、それを差し引いてもその経験が劇団活動のその後に大きな影響を与えただろうことは想像に難くない。
前置きが長くなったが、「劇トツ×20分」はとても良い形で続いた企画だったと思う。その集大成として最終回の今回は、歴代チャンピオンが上演して「チャンプ・オブ・チャンプ」を決める頂上決戦だった。今やすっかりなじみの劇団ばかりだ。懐かしい作品も、新たな作品も、「らしさ」にあふれ見応えがあった。以下、簡単に感想を。

劇団言霊『クーリングラブ』(作・演出:山口大器)
2019年に初めて見た時に、ラストの傾斜角度のある台の上に立つ「出兵する男」と手前にいる彼の恋人を画角に入れた空間の使い方にとても感心した。また小道具を使った表現方法にも唸った。それは紙飛行機として届く赤紙を届けるというもの。その「軽さ」が、人間の命の軽さ(扱われ方の軽さ)と重なって、センスがあるなと思ったものだ。
今回は小劇場から中劇場に舞台が大きくなったせいか、ラストシーンの台の置き位置が私の記憶と違う。前回は確かど真ん中に置かれて、台の上に立つ男は客席正面に向って言葉を発していた。今回は下手奥側に置かれ、男は上手前方に向って語る形だ。たったこれだけの違いなのだが…空間がだだっ広く感じられてしまい、身に迫るものが失われてしまった印象となった。男の言葉の意味、つまり恋人への想い、生きることへの渇望が、届きにくいと感じたのだ。良い作品なだけにもったいないと思った。
F’s Company 『はいけい』(作・演出:福田修志)
バスの中での一幕。別れがたく「ロミオ&ジュリエット」になりきっている男女と、2人を取り巻く観客たちの状況の落差、思い出す「何か」を演技で見せる作品。新作である。こういった、場面だけを切り取ってそこから膨らませて作品にしてしまうのが、とても演劇的で、いい。役柄をどんどん変えていって飽きさせず、役者の演技も堪能した。
ブルーエゴナク『瀬戸際の旅』(作・演出:穴迫信一)
妹が、死んだ姉の好きな人と姉の葬儀前に旅するシュールな作品。弔辞(?)で締められていて、実は2人の会話は、妹の、あるいは恋人の、頭の中だけのことだったのかとふと思う。チャレンジングな作品だ。役者が違えば雰囲気も一変しそうである。
万能グローブガラパゴスダイナモス『僕は笑わせることしかできない』(作・演出:川口大樹)
舞台の広さが変わったことで、笑いが縮小した印象である。広さに合った笑いというものがあって――弱気であまり能力がありそうにない、あの「笑いの神様」には、小劇場の方がぴったりだ。(役者のせいではないことを書いておきたい。)笑いと泣き(人情味)があって良い作品なのだが。
不思議少年『スキューバ』(作・演出:大迫旭洋)
本作は、前回の劇トツでの上演とあまり印象が変わらない。水中を漂っている気分にさせる作品。絵本の話であり彼女の一生の話であり、…そう人の生とはまるで絵本の物語だと言っているようだ。空気がキラキラ輝いて、柔らかい印象を与える稀有な作品だと思う。笑わせたり跳んだり跳ねたり踊ったり、3人の役者がそれぞれに本領発揮している。優勝作と1票差。
劇団ヒロシ軍『一寸先はYummy!!Yummy!!(2023Ver.) 』(作・演出:荒木宏志)
20分のエンタメとして、(言葉は悪いけれど)箸休め的に楽しめる作品。山神さまだとかつき合うつき合わないだとか、ちょっとよくわからない弾けた歌の応酬なのだが、不思議な事に彼の作品は「自己満足」的だとは感じない。荒木宏志さんの人柄なのだろうか? 客席の「待ってました!」感が強くて、人を楽しく巻き込む力に感心。
PUYEY『おんたろう』(作・演出:高野桂子)
舞台が広くなった割に余白を感じさせなかった。それは、誰が見ても「あるある」と思い当ったりうなずけたり感情移入できるために、集中しやすいからだろうか。今どきこういったメッセージ性のある作品は珍しいのかもしれないが、おんたろうというとぼけた風貌の味のある存在を出すことで、全体としてほんわかとした印象を残すことに成功している。言いたいことも言えない、周囲に気遣って生きる人が多い(特に若い人!)この時世に即した作品である。
おんたろうが変わり身の術(笑)を使った時も、やっぱり客席はどっと沸いた。素朴なのに観客がやっぱり騙されて(あるいは知っていても)笑ってしまう、良い空気を生む作品だと思う。優勝おめでとうございます。

劇トツ×20分、長きに亘って楽しませてくれたこの企画に、感謝!
2023.08.16
カテゴリー:
2023年7月16日(日)14:00~ @大濠公園能楽堂

●ふくおか「萬斎の会」
「食」
小舞・野老 (野村萬斎)
狂言・苞山伏 (高野和憲・月崎晴夫・深田博治)
狂言・栗燒 (野村万作・内藤連)
狂言・宗論 (野村萬斎・野村裕基・中村修一)
野村萬斎は、普段の喋りより狂言の時の声がいい。演目が始まる前に、本日のテーマと演目の解説をしてくれたのだが、それより狂言の時の方が、声も活舌も良く聞こえた。不思議だ。今まで彼の狂言も現代演劇も、どちらも見ていたのだが、初めてそんなことを思った。
さて本公演のテーマは「食(じき)」だという。『小舞 野老(ところ)』『狂言 苞山伏(つとやまぶし)』『狂言 栗燒』『狂言 宗論』の4本立て。狂言において、飲み物も含めた「食」はよく出てくる題材だ。学校の教科書に出てきた『附子』もそうだし、『柿山伏』も有名だ。「禁じられているものを食べた」だの「こっそり食べた」だの、子どもがやりそうなことを大の大人が後先考えずにやってしまうことばかり。無邪気というか、浅はかというか。多くが権力者への意趣返しにもなっているので、食べ物ていどの仕返しはかわいいものともいえる。お金や武器が登場するような生々しい反抗となると、もはや笑いというより復讐劇で、狂言ではなくなってしまうからね。そういえば、『茸(くさびら)』という演目を見たのを思い出す。キノコと山伏の戦いの話で、山ほどのキノコ(を演じる立衆)が続々と登場してきて、とてもびっくり、そして大笑いした。人間の基本は食だから、人間を愛しみながら笑う狂言が食を扱うのは当然か。
特に食に注目すると、いつもとは違った面白さにも気がついた。例えば『苞山伏』での食べっぷりである。苞(つと)とは納豆が入っているような藁でできた保存容器のことらしく、つまりはお弁当だと思えばいい。それを脇につけたまま寝入っている山人を見つけた山伏がこっそりと苞を食べるのだが、その時の様子と言ったら、藁を親指で押し開いて中のものを口にやるしぐさが何ともリアル。ここでの演技は誰が演じてもそうするのか、今回の山伏役の深田博治だけの演技なのかわからないが、そのモグモグタイムの可愛いこと、面白いこと。
『栗燒』は栗が焼ける様子の音が面白い。狂言にはもともと音楽や効果音がなく、色んな音をオノマトペで表す。太郎冠者(野村万作)が主人に命じられ40個の栗を焼くのだが、その時の音が豊かなのだ。シューシュー、ぽん、ブツブツ。失礼ながら齢90を超える万作がオノマトペをとなえるとかわいらしくも見える。狂言では「ドブドブドブ」と酒を注いだり「クックック」と飲んだり(そう聞こえる)「あむあむあむ」と食べたりと、オノマトペは定型化されていてそこが面白さの一つでもある。何となく「オノマトペの文字が見えるようだ」といつも思う。マンガに出てくる文字化されたオノマトペのあれである。登場人物の行動の単純さも加わって、狂言ってマンガに共通するところがあるのかもしれない。

他2作は、言葉で食と戯れる作品だった。『野老(ところ)』は変てこりんな話で、野老(=山芋)の亡霊が、自分が土の中から掘り起こされて調理されて食べられてしまう様子を地獄のようだと嘆いて舞う話だ。配布された謡の詞章を見ると、食べ物の名前がいっぱい、しかもダジャレである。それに、山芋の立場で(鶏や魚ならまだわかるけれど)食べられる苦しみを舞うって…かなりぶっ飛んでいる。『宗論』は宗教論争をする話だが、ここでも言葉遊びのような形で料理が登場する。(情けないことに私は萬斎の解説がなかったらよく分からなかっただろう。)直接的に食べ物を小道具にして笑いを誘う『苞山伏』『栗燒』と違って、食べ物の気持ちになったり食べ物で言葉遊びをしたりと、一風変わった面白さである。狂言の笑いもバリエーションに富んでいるのだと学んだ一日だった。
追記:「万作の会」もそうだが、親子三代(野村万作・萬斎・裕基)での舞台、演る方も見る方も幸せなことである。
2023.08.05
カテゴリー:
2023年7月9日(日)15:00 @山口情報芸術センター・スタジオB

●ハイバイ
『再生』
演出:岩井秀人
原案:多田淳之介(東京デスロック)
出演:日下七海、小宮海里、田中音江、つぐみ、徳永伸光、南川泰規、乗松薫、八木光太郎、山本直寛
『再生』を見るのは三度目である。最初は、東京デスロックによる初期の『再/生』を2012年ぽんプラザホールで。セリフもなく、ただ役者たちが踊り狂って倒れていき、また再生して踊り狂って…を3回繰り返す。とにかく衝撃的だった。役者(あるいはダンサー?)の疲弊していく身体と、澱んでいくかに思える空気(酸欠状態?)、さてこれは「再生」の物語なのか、「死に向かう」物語なのかと混乱して絶句した。二度目はそれから10年後、2022年に北九州芸術劇場にて。今度はセリフもあり、より初演(2006年)当初の「集団自殺をする若者たちの宴」というモチーフが明らかになっていた。しかも出演者の20代バージョンと同時に40代バージョンも作られ(残念ながら後者は見られなかったのだが)面白い広がりがあるものだと感心した。作りは前回と同じで、全員が踊り始めて倒れ死に到達するまでを3回繰り返す。ただ1度目の作品と違うのは宴会シーンがあること。そこでの彼らは明るく楽し気ではあるが、会話は極めて表層的で、その後に続くハイテンションのバカ騒ぎも軽く感じられる。彼らの行動の意味に物語性を見出すことになり、私には「繰り返す意義」があまりないように感じた。
そうして3度目の今回は、原案の多田淳之介(東京デスロック)ではなく岩井秀人(ハイバイ)演出による『再生』である。一言で表せば「最後の最後までワクワクさせる作品」だった。

舞台奥から半分囲む形で階段状のブリッジがある。手すりが大小の□になっていて青紫がかった暗くて妖しい空間の中でも際立って見える。そこに色とりどりの衣装の9名が不規則に倒れている。…そこにダフト・パンクの『One More Time』が流れ始め…順番に起き上がり立ち上がり、全身全霊で動き回り踊り始めた。彼らは6曲の音楽が流れるあいだずっと踊り続け動き続け、最後のBanvox 『Laser』の曲が終わる頃に一人、また一人と倒れて息絶えていく…これが3回繰り返される。

ワクワクさせられたのは、奇抜で目を引く衣装のせい(藤谷香子)もあるし、彼らの運動能力のせいもあるだろう(汗が落ちるさま、汗で体にまとわりつく衣装、少しずつ息が上がる様子、もあるのだが、驚くほどに再現性が高く、そして手を抜かない踊りである!)。また蛍光色のレーザー光線、風船やら突如として体に巻き付けたライト、ミラーボールを天に返すしぐさ、頭に載せたリンゴを別の誰かが食べる、といった心浮き立つ小道具のせいでもある。忘れてはならない、選曲のセンスにもニヤリとする。だがなにより、多様な想像力を喚起させる「イメージの遊び」が本作にはある。
たとえば、殴り合いのようなジェスチャーの後で倒れていき、しばらく後に起きあがって同じことをくり返す様子はゾンビにも見える。死を恐れず、痛みもない、永遠に「生/死」をさまようだけの存在。彼らの動きの再現性が高いだけに(3回とも動きが正確に同じ)、彼らには時間の存在がないように見えた。「存在しない時間」を感じるのは面白い。
チラシに「命のお祭り」という文字が躍るが、生と死を扱う作品に祝祭性は欠かせないだろう。彼らの反復は儀式のようにも見えるし、それによって禁忌を破る(=死へと向かう)ことを示唆しているともいえる。昨年見た『再生』(セリフ有の宴会から死へと向かう作品)は、「服毒し、ハイテンションになって踊り、死に至った」のだが、それは死への恐れや緊張からの興奮が踊らせたように見える。だが本作での踊りは「日常からの逸脱、社会的秩序の逆転」の象徴に見え、だからこそ「日常(生)/非日常(死)」の狭間をさまよう祝祭の儀式にも見える。この祝祭性の高さが、本作の重要な点だろう。

また本作に生物が持つ生命力も見える。わずかなダメージなんてものともしない生への執念深さ。それも9名の役者の姿が苦しんだりもがいたりしていないために、一個体の話ではなく、種レベルでの生命への執念を感じる。種としての生命力の強さ。
同様に、いずれは朽ちる身体(個体)と、それでも繋がって遺っていくDNA(種)にも思いが行く。劇場を出た時にらせん状の舞台イメージ模型が置かれていたが、「目に見えないのに確かにある(と思う)生命、受け継がれていく生命とは何だろう」と思考が広がっていった。
だから見ている間ずっとワクワクしていたのだろう。そして私もその一部なのだという喜び。なんて豪快でスケールの大きな、生命の祝祭なのだろう!
乾杯したいと思った。全ての生命に。
追記:終演後の「岩井バー」で見知らぬ観客が「(劇中に登場した)ペットボトルは、『リサイクル=再生』ってことなのかなと…」と一言。なるほど!
2023.08.02
カテゴリー:

- 2026年1月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年7月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 『証明』Level 19
- 『Re:北九州の記憶~未来へつなぐ物語 石炭の走る街』北九州芸術劇場+市民共同創作劇
- 『きらめく星座』こまつ座
- 『宇宙船イン・ビトゥイーン号の窓』チェルフィッチュ
- 『恋はみずいろ』「老いと演劇」OiBokkeShi
- 『受胎の森』ゴブノタマシイ
- 『人形の家をたずねて』加茂慶太郎×cobaco ohori house
- 『轡田市猿田校区年度末区民会議』非売れ線系ビーナス
- 『おかえりなさせませんなさい』コトリ会議
- 『白/道』Project Lotus idea

●月に一度、舞台芸術に関係するアレコレを書いていきまーす●
大学院時代から(ブラジル滞在の1年の休刊をはさみ)10年間、演劇批評雑誌New Theatre Reviewを刊行。
2005年~朝日新聞に劇評を執筆
2019年~毎日新聞に「舞台芸術と社会の関わり」についての論考を執筆
舞台、映画、読書をこよなく愛しております。
演劇の楽しさを広げたいと、観劇後にお茶しながら感想を話す「シアターカフェ」も不定期で開催中。
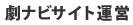
「劇ナビFUKUOKA」は、株式会社シアターネットプロジェクトが運用管理しています。
株式会社シアターネットプロジェクト
https://theaternet.co.jp
〒810-0021福岡市中央区今泉2-4-58-204